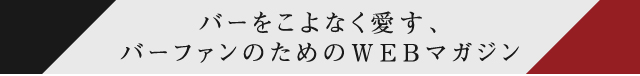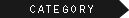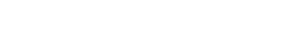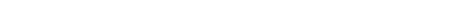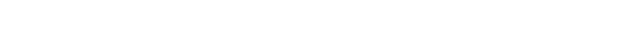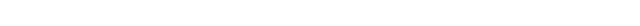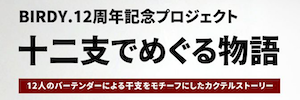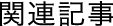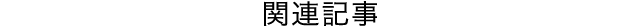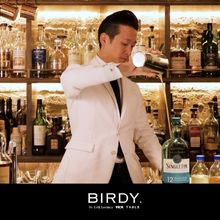2025.04.14 Mon
新たな魅力を発見するプレミアムテキーラの世界テキーラの製法
林 生馬(日本テキーラ協会会長)テキーラの主原料はアガベアスール。
アガベが成熟するまでに4〜10年と幅があり、土の質や蒸留所での需要を鑑みて栽培する。
栽培年数が長いほど糖度が上がるだけでなく、重合度が上がり、それによってミルキーでクリーミーな甘さを醸す。酒の主原料は麦、米、葡萄、芋、とうもろこし、サトウキビなど毎年収穫できるのが一般的であるが、アガベだけが複数年栽培となり、独特な柔らかくクリーミーな甘味を持つ。
収穫には「ヒマドール(Jimador)」と呼ばれる熟練した職人が行い球茎部ピニャを取り出す。ここで皮を残せばテキーラが辛くなり、皮を深く剥けば辛さは回避できる。芯を残せばテキーラは苦くなり、捨てれば苦味は回避できる。

主原料であるアガベアスール。

ヒマドールがコアと呼ばれる長い柄の先に丸い刃がついた道具で、頑丈なアガベの葉を削ぎ落としていく。

皮を残すか深く剥ぐかでテキーラの味わいが変わる。
ピニャは、糖を抽出しやすくするためにオーブンで蒸し焼きにされる。
伝統的な方法では石造りの蒸し窯マンポステラを使い、36〜48時間じっくりと蒸す。それによりピニャの表面がメイラード反応でカラメル化し、キャラメル香を出す。
近代的な工場では圧力窯アウトクラベを使い、6〜12時間で糖化させることもある。その場合はキャラメル香よりもハーブ香が活かされることもある。

石造りの蒸し窯マンポステラを使い、じっくりと蒸すのが伝統的な方法。
加熱されたピニャを粉砕し、糖分を含んだ甘いジュース(アグアミエル)を抽出する。
伝統的な方法ではタオナ(Tahona)と呼ばれる大きな石車を使ってすり潰す。現在でもタオナを使用する蒸溜所が少数あるが、これは石車で押し潰した後の残る搾りかすバガスを発酵槽に入れて一緒に発酵させ、テキーラに麦わらのようなバガス香を得るためである。
近代的な工場では、ローラーミルを使用して効率的に搾汁する。

搾汁においては、タオナ(Tahona)と呼ばれる大きな石車を使ってすり潰すのが伝統的。

ローラーミルを使用して効率的に搾汁する工場もある。
抽出したアグアミエルに加水して糖度を10前後まで落とし、発酵槽(木製またはステンレス製)に入れ、酵母を加えて発酵させる。
自然酵母を使うこともあるが少数派で、多くの蒸留所では一貫した品質を保つために特定の酵母を発酵槽に加える。酵母は蒸留所により異なるが、特徴的なのはクエルボ家に伝わる門外不出のクエルボ酵母で、他の蒸留所には無い独特のクエルボ香をもつ。
3〜7日間の発酵により、糖分が、アルコール、二酸化炭素、熱に変わるのは、他の酒と同じである。
発酵後に得られた醸造酒モストを2回蒸留するのが一般的。
初留(第一回蒸留):アルコール度数が約20〜25%になり、オルディナリオと呼ばれる。まだ少し白く濁っている。
再留(第二回蒸留):アルコール度数が約50~55%になり、完全に透明。これがテキーラの原酒である。
蒸留器には単式ポットスチルが多く使われ、連続式は少数派である。

抽出したアガベジュースに加水し、酵母を加えて発酵させる。発酵後に得られた醸造酒モストを単式ポットスチルで蒸留。
蒸留後、テキーラはオーク樽で熟成されるものがある。熟成期間により以下の種類に分類される。
⚫︎ブランコ(Blanco)/熟成期間は0〜2ヶ月。フレッシュでアガベの風味が強いのが特徴。
⚫︎レポサド(Reposado)/熟成期間は2ヶ月〜1年。オークの香りが加わり、まろやかなのが特徴。
⚫︎アネホ(Añejo)/熟成期間は1年〜3年。深いコクと複雑な味わいが特徴。
⚫︎エクストラアネホ(Extra Añejo)/熟成期間は3年以上。濃厚でリッチな風味が特徴。
樽熟成の期間が短めなのは、テキーラが暑いからである。天使の分け前は年間15%。またテキーラではソレラ熟成もほとんどない。

樽熟成の期間によってテキーラに様々な味わいの変化が現れる。
アルコール度数を調整し(通常35〜40%)、一般的には3~4回のフィルタリングの後、ボトルに詰められる。フィルターで除去されるのは主に脂分である。フィルタリング回数が1回で少ないとオイリーでボディ感があるが、開栓後にオイル分が酸化してしまうリスクもある。
100%アガベのテキーラは、必ずメキシコ国内で瓶詰めされる。
文/林 生馬(日本テキーラ協会会長)
1968年東京生まれ。カリフォルニア州で映画制作スタッフとして活躍。ハリウッド・ビジネスの中枢で活動中に周囲の影響からテキーラに出会う。映画スタッフらをはじめ、ショーン・コネリーや北野武監督らとテキーラを酌み交わす経験を得て、テキーラの最先端の飲み方およびテキーラブームの到来を目の当たりにする。訪れた蒸留所は100を数えテイスティングした銘柄は2000を超える。テキーラ蒸留所のスタッフやテキーラ・アンバサダーとの親交も深く日本へ帰国後2008年7月に「日本テキーラ協会」を創立。メキシコ大使館やFOODEXをはじめ、日本全国の会場でテキーラの講習会を行う。著書に「テキーラ大鑑(廣済堂出版)」 TVやラジオ、新聞、雑誌など各種メディアへの出演多数。