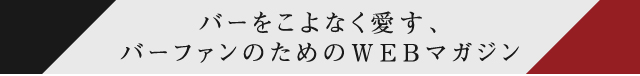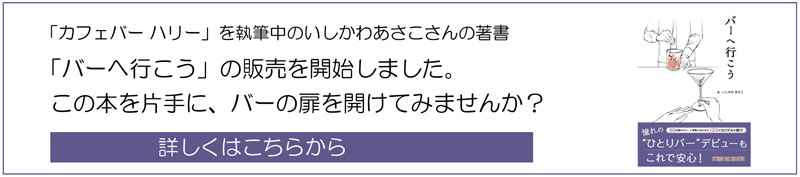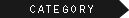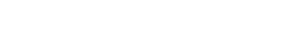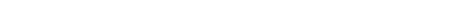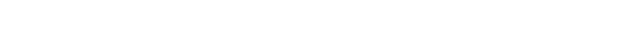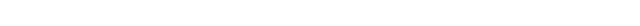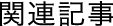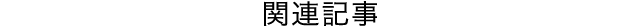2019.06.19 Wed
コラム:カフェバー ハリー第6話 「たくさんの笑顔に囲まれて」
文:いしかわあさこまもなく二十歳を迎える専門学校生のジュンは、「カフェバー ハリー」を営む夫婦のひとり娘。高校時代から店を手伝っているが、両親の仕事にさほど興味はない。ところが、二十歳を迎えた頃からぼんやりと将来を考え始め、店に訪れる人たちとの交流を通じて徐々に両親の仕事、お酒の世界の魅力に気づいていく。
第6話 「たくさんの笑顔に囲まれて」
どうしよう。私に務まるだろうか。いや、やってみなくちゃわからない。でも、迷惑をかけるかもしれない。でも……そんな葛藤は、十秒もかからなかった。
「私、やってみようかな」
両親は揃って目を丸くしたが、母のひと言でその日の営業が決まった。
「じゃあ、お願いするわ」
いつも体調管理を万全にしている母が、前夜から調子が悪いという。今夜はアルバイトの人もいないし、店を休みにしようか、簡単なものだけ出すことにするか、朝から両親が話しているのが聞こえてきて、自分の部屋から隣の居間へ向かう間にカウンターに立とうと決心した。これまでカウンターの中に入ることはあっても、洗い物をするだけでお客にお酒を作ったことはない。ただ、二十歳の誕生日を過ぎてから、こっそりカクテルを作る練習はしていた。
最初のお客は、大野さんだった。いつものジン・トニックを作ろうとメジャーカップを取ると、手ががくがくと震えた。人前でカクテルを作るだけなのに、これほど緊張するなんて予想外だ。
「ん~、美味しいね。たくさん練習したでしょう」
大野さんが、カウンターでにこにこしている。やがて寺田さんもやって来て、気づけば週末でもないのにカウンターがほぼ埋まってしまった。猫の手も借りたいよ……そう頭の中で呟いたとき、横から手が伸びてきた。
「薬が効いてきて、もう大丈夫だから」
母がテーブルに残ったグラスやお皿を次々に集め、洗い始める。少し心の余裕ができて周りを見渡すと、いつもと立ち位置が逆になった店を、常連さんたちは楽しんでいるようだった。
「ジュンちゃん、カクテルとても美味しかったよ。ありがとう」
「あっ、ありがとうございます!」
寺田さんが笑顔で手を振り、店を出た。徐々にお客が引けて落ち着くと、父が賄いを作るという。急におなかがグ~っと鳴った。
「今日は助かったよ。これからもなんかあったら頼むな」
力になれたんだ、と思った途端、お客さんたちの笑顔がちらついて、なんとも言えない達成感に包まれた。とてつもなく疲れたのは確かだが、それを上回る何かが込み上げてくる。
「知ってたわよ。練習してるの」
母が私の肩に手を置いて言った。あっさりと私に任せたのは、そういうことだったのか。
「ねえ、バーテンダーってもしかしたら人を笑顔にできる職業なのかもね」
「そうでありたいと思ってるわ」
このカウンターで、私はもっとお客さんを笑顔にしたい。楽しんでいる姿が見たい。美味しいカクテルを作りたい。
「バーテンダー、目指してみようかな」
小声だったから聞こえてないかも、と振り向くと父と母が微笑んだ。
いしかわあさこ
東京都出身。飲食業からウイスキー専門誌『Whisky World』の編集を経て、バーとカクテルの専門ライターに。現在は、世界のバーとカクテルトレンドを発信するWEBマガジン『DRINK PLANET』、酒育の会が発行する冊子『Liqul』などに寄稿。編・著書に『The Art of Advanced Cocktail 最先端カクテルの技術』『Standard Cocktails With a Twist~スタンダードカクテルの再構築~』(旭屋出版)『重鎮バーテンダーが紡ぐスタンダード・カクテル』(スタジオタッククリエイティブ)がある。愛犬の名前は、スコットランド・アイラ島の蒸留所が由来の“カリラ”。2019年4月、新刊『バーへ行こう』が発売。
第1話 「週6日の常連客」
第2話 「カウンターに立つ母」
第3話 「二十歳の誕生日」
第4話 「バイオリンの音色が響く夜」
第5話 「バーが繋ぐもの」
第6話 「たくさんの笑顔に囲まれて」